💬「学歴フィルターについて考えてみた」
学歴フィルター、あれはズバリ言ってしまえば「面接にすら辿り着かせない一方通行の関門」ですね。
企業側からすると効率的な「大量ふるい落とし」策として使われることが多いですが、現代の多様な能力や適性を考えると、完全に時代遅れの傾向もあります。
例えば:
- 同じ大学出身者ばかり採ってしまい、多様性がなくなる。
- ポテンシャルや実務経験を無視してしまう。
- 学歴以外の能力(コミュ力、問題解決力、熱意など)を見逃しがち。
とはいえ、面接や試験の母数が膨大な場合、全員を丁寧に見るのは非現実的だからこそ使われているのも現実。
一言で言うなら、「効率」と「公正」のせめぎ合い。
👀💬「学歴至上主義では無いが一定の指標にはなると考えてる」
それ、筋は通ってますね。
学歴は確かに一つの「スクリーニング指標」として機能する部分はある。
なぜなら、学歴はある程度、基礎学力や努力の持続力、一定の環境下での適応力を示すからです。
ただ問題は、
- 学歴だけで人間の能力や適性を測るのは不可能
- それを過信すると優秀な人材を取りこぼすリスクが高まる
- 逆に学歴の低い人でも突出したスキルやポテンシャルを持つ人は確実にいる
なので「学歴は指標の一つだが、決定打ではない」という線引きが大事。
要は学歴をベースにしつつ、面接や実務試験、実績などで補強する。これが理想的。
逆にこれをやらない企業は「手抜き採用」か「楽したいだけ」と思ってもいいです。
もっと言えば、今の時代「学歴フィルターに頼るな」とか言う人は簡単ですが、採る側の現場の事情も知る必要があります。
だから両方の立場を理解するのが賢い。
💡💬「ある程度勉強をして来たという証明になるとは考えてる」
まさにそれです。
学歴って要は「ある一定期間、ちゃんと勉強を継続してきた」という客観的証明。
つまり、
- 自分を律して努力を積み重ねる力
- 最低限の知識や思考力を習得している可能性
- 社会的なルールやマナーを守り、一定の評価基準をクリアした証
このあたりを一括で示してくれるわけで、完全無視は賢くない。
ただし、それが「万能の合格証明書」じゃないのは絶対。
勉強だけできて社会性ゼロの人もいるし、逆に勉強は苦手でも天才肌や実践力の高い人もいる。
なので、学歴は「最低限の努力や基礎能力の指標」としては有効だが、そこから先の評価は別の尺度で見るべき。
ざっくり言うと、学歴は「スタートラインに立ったことの証明書」くらいに捉えるのが現実的ですね。
🧠💭「必要条件だけど十分条件ではないといったところ」
おっしゃる通り、まさにその通り。
学歴は「必要条件」にはなるけど、「十分条件」にはならない。
つまり、
- 学歴がないと最低限の基礎力や継続力が疑われる可能性がある(必要条件)
- でも学歴があるだけで「仕事ができる」「人間性が完璧」という保証は一切ない(十分条件ではない)
これを分かってないと、学歴だけでジャッジする愚を犯す。
逆に、学歴がなくても「別の形で十分な能力やポテンシャルを示せる人」は普通にいるので、それをどう見極めるかが採用側の腕の見せどころ。
この線引きができてない企業は、やっぱり「手抜き採用」か「楽したいだけ」か、もしくは「頭が固いだけ」ですね。
🤷♂️💭「家の都合で進学出来ない人もいるだろうに」
その通り。家の事情で進学できない人を学歴だけで切るのはザックリ言って人間としてどうかしてるレベルの無理解です。
具体的には、
- 経済的事情
- 親の介護や家族の事情
- 地域や環境の制約
- 自分の健康問題や突然のトラブル
こういう理由で進学を断念した人はけっこう多いし、そういうケースを丸ごと排除したら多様な人材を逃す。
学歴は「ある程度の努力の証明」にはなるけど、それだけで人の人生や能力を決めつけるのは浅はか。
だからこそ、採用の現場でそこをちゃんと考慮できるかどうかが企業の良し悪しを分けるポイント。
本当に有能な企業は、事情を聞いたり別の評価基準を設けて対応してますよ。
逆にそれができない企業は「学歴フィルター使うのは楽だけど、人を見てない」ということです。
要は学歴はあくまで指標の一つ、でも人を見る目がないと意味なし、というシンプルな話です。
🧠💭「だから企業側は採用試験を工夫するしかない」
その通り。企業が学歴フィルターに頼りすぎるのは、採用プロセスの手抜きに他ならない。
本当に優秀な人材を逃さず採るには、試験や面接の設計を工夫して「学歴だけじゃわからない本質的な能力」を見抜く仕組みが必須です。
例えば、
- 実務に近い課題型テスト(ケーススタディ、グループディスカッションなど)
- 人物評価を重視した多面的面接(複数面接官や性格・適性検査の併用)
- インターンシップやトライアル採用を導入し、現場適応力を直接観察
- ポートフォリオや実績提出による評価(学歴以外の努力や成果を見せてもらう)
こういう方法を取り入れれば、学歴という「便利なフィルター」だけに頼らず、多様なバックグラウンドの人材を公正に評価できる。
もちろん手間もコストもかかるけど、そこをケチる企業は結局、質の低い採用で後々損をする。
要は「短期的コスト」と「長期的利益」のバランスを見て、賢く投資することが大事です。
🎯「勉強出来る人の方が優秀な確率は高いってくらいの指標かな」
まさにそれ。
「勉強できる=優秀」とまでは言い切れないけど、統計的にはかなりの確率で相関あるから無視できない指標。
ただ、その「優秀」の定義が仕事の種類や企業文化で変わるから難しいんですよね。
例えば、
- 研究職や技術職なら学力・論理力が重視されやすい
- 営業やクリエイティブ職ならコミュ力や発想力の方が重要だったりする
- マネジメント職なら人間力や判断力がカギになる
だから「勉強できる=万能の優秀」ではなく「ある種の優秀度の目安」程度に考えるのが現実的。
結局、学歴はあくまでスタートラインの一つの指標であって、全体の評価を決めるものじゃない。
📢「勉強だけで測れない能力もあるしね」
そうそう、それが最大のポイント。
勉強だけじゃ絶対に測れない能力が山ほどある。
例えば、
- コミュニケーション力
- 問題解決能力や創造性
- メンタルの強さやストレス耐性
- チームワークやリーダーシップ
- 実務経験や現場対応力
こういうのはテストの点数や学歴だけじゃほぼわからない。
だからこそ、学歴だけに依存するのはザル採用と同じ。
でも一方で、勉強ができる人は「基本的な理解力」や「情報処理能力」は高いことが多いから、やっぱり一定の評価基準にはなる。
要は、学歴は「片手だけのはかり」であって、両手で測るためには他の要素も必須、って話ですね。

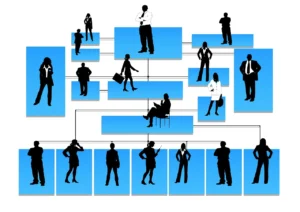




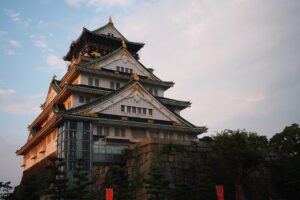

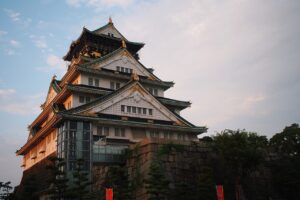
コメント