💬「以前中国の経済について書いたがロシアはどうだろう?」

中国経済の現状と展望(2025年)
1. 中国経済は確かにヤバい、でも「崩壊」はしない
- 不動産バブルの崩壊(恒大集団・碧桂園など)
- 若年失業率20%以上(※公表中止)
- 外資の脱中国・生産シフト(チャイナプラスワン)
- 消費不振と内需停滞
とはいえ、中国は「資本主義の皮を被った国家資本主義」。
国営銀行・国有企業・政府系ファンドがフル稼働しており、「ゾンビ経済」でも延命可能な体制が整っている。
2. 株価が一時的に回復している理由
- AIやEVなど一部新興セクターが市場を牽引
- 政府系ファンドによる「国家隊」の株買い支え
- 外資の一部再流入(短期筋中心)
ただし実体経済は回復しておらず、株価はあくまで政策主導の“張りぼて”状態。
PERや成長率と乖離しており、持続性に乏しい。
3. 「崩壊しようがない」3つの理由
- 人民元建て経済圏:外債依存が少なく、デフォルトは国内で処理可能
- 国家の金融・政治の一体構造:中央銀行・銀行・監督官庁が一体
- 強力な統治能力:
- 政治統制(習近平の個人独裁体制)
- 監視社会(天網システム・顔認証・信用スコア)
- 軍隊が中国共産党の直轄(反乱の可能性ゼロ)
つまり、経済よりも統治の安定性が圧倒的に強い国。
4. 「失われた30年型」長期停滞に突入する可能性
- 少子高齢化と労働力減少
- 家計債務の増加
- 地方政府の債務危機
- 革新的産業の「中途半端な模倣型」
→「成長より安定」「躍進より維持」がキーワード。
日本のバブル崩壊後のような**“国家主導の長期沈滞”に入る可能性大**。
5. 政治・軍・公安の「鉄壁トリオ」で秩序は盤石
- 習近平の権力集中(任期制撤廃)
- 軍隊・公安・武警の忠誠は個人に直結
- SNSやメディアは完全に監視・統制
反政府デモや革命など、西側のような「ボトムアップの揺らぎ」は構造的に起きにくい。
総まとめ:中国は「崩壊しないが、苦しみながらも生き続ける巨人」
中国経済は今、
✅ 問題だらけだが、
✅ 制度上崩壊しようがなく、
✅ 長期停滞を国家主導で受け入れる段階に入っている。
「中国崩壊論」はむしろ西側の願望や幻想に近く、
現実の中国はもっとしたたかで、したたかに停滞する。
🤷♂️💭「ロシアも似てるが状況は深刻」
おっしゃる通り。ロシアも「崩壊しない国家」ですが、中国とは似て非なるヤバさを抱えています。以下に比較しながら、ロシアの深刻さを整理します:
ロシア経済の現状と深刻なポイント(2025年)
1. 戦時経済への突入と構造劣化
- ウクライナ戦争の長期化により、通常の経済活動は事実上停止
- GDPは軍需関連で下支えされているが、民間投資・外資は壊滅状態
- 徴兵と脱出で労働力が減少、産業の持続性に疑問符
→「戦争のおかげで生き延びている」という歪んだ延命が続いている。
2. 西側からの経済制裁と孤立
- SWIFT排除、資産凍結、ハイテク禁輸などの制裁により、金融と技術が致命的に劣化
- 中国・インドなどと裏ルートで貿易継続しているが、条件は完全に不利(買い叩かれ状態)
- 通貨ルーブルは一時安定も、原油価格頼みの危ういバランス
→**「友達はいるが、全部立場が下」**という孤立状態。
3. 資源頼みのモノカルチャー経済
- 原油・天然ガス・穀物など資源輸出に極端に依存
- ハイテク・製造業は壊滅(半導体、機械、航空機など)
- 制裁により部品の「カニバリズム経済(旧製品を壊して使う)」が横行
→経済の多様性ゼロ。21世紀のソ連状態に逆戻り。
4. 強権体制は維持されているが、足元は不安定
- プーチン体制はなお強力だが、プリゴジン事件など、内部の不満が噴出し始めている
- 若者・都市部の知識層の国外流出が止まらず、社会の知的劣化が加速
- 地方と都市、老人と若者の分断が深刻
→国家は「鉄の外装」だが、中身が崩れてきている印象。
5. 「崩壊はしないが、後戻りできない深刻さ」
- 政治・軍・治安機構で抑え込めてはいるが、経済・社会の劣化スピードは中国以上
- しかも出口がない(戦争やめれば崩壊、続けても崩壊)という構造
総まとめ:中国=「停滞する超大国」、ロシア=「持ち堪える限界国家」
| 項目 | 中国 | ロシア |
|---|---|---|
| 経済基盤 | 製造業・内需あり | 資源依存型 |
| 政治体制 | 一党独裁だが制度的 | 個人独裁化が極端 |
| 外交状況 | 不満はあれど関係維持 | 完全に制裁&孤立 |
| 社会統制 | 高度監視・安定 | 力ずく・脆い安定 |
| 将来性 | 停滞だが制度は維持 | 崩壊寸前の綱渡り |
えすえふさんの言う通り、ロシアの方が深刻。
一言でまとめるなら:
中国は老化しているが、ロシアは壊死が始まっている。
👀💬「アサド政権崩壊は兆候な気がする」
その視点、鋭いです。
「アサド政権の崩壊兆候」──これは中東地政学において、ロシアの地盤沈下を示すサインとも言えます。
以下、背景・現状・今後の展望を整理します:
【アサド政権崩壊の兆候】
―ロシア・イラン体制の終わりの始まり―
1. 背景:アサド政権は「ロシアの傀儡」だった
- シリア内戦(2011年~)で一時は崩壊寸前だったアサド政権を救ったのがロシアとイラン。
- 特にロシアは2015年から空爆を開始し、アサド=ロシアの代理人政権として延命。
- シリアはロシアにとっての**地中海への軍事拠点(タルトゥース港)**でもある。
つまり、アサド政権の安定は「ロシアの中東影響力の象徴」だった。
2. 現在の崩壊兆候:内部崩壊+外部離反のダブルパンチ
✅ 経済崩壊
- 通貨価値の下落、燃料不足、食料価格の暴騰
- イラン・ロシア双方からの支援が細り、国内経済は事実上機能停止
✅ 反体制デモの再燃(2023年末以降)
- スウェイダ県などで「アサド退陣」を叫ぶ抗議行動が継続
- アラウィ派(政権支持母体)内部でも動揺が拡大
✅ アサド側近・軍の分裂兆候
- 情報機関幹部や地方軍閥が**「自分の身の安全」を優先して動き出している**
- これは体制崩壊の前兆で最もリアルなサイン
3. ロシアの後退が致命的要因
- ロシアはウクライナ戦争で中東どころじゃない状態
- シリアへの支援や空爆は激減、イラン任せにシフト
- 一方、イランもイスラエルとの戦争リスクや国内不安定化で手一杯
→つまりアサド政権を支えてきた「外部パトロン」がどっちもガス欠。
4. 中東全体への影響:新たな地政学のシグナル
- アサド崩壊 = ロシア・イランの中東後退
- トルコ・アラブ連合・イスラエルが新秩序を模索
- サウジがアサドに距離を置き始め、湾岸諸国も利害重視に
一言で言えば:
アサド政権の揺らぎは、ロシア・イラン陣営の「縮小戦線」の最前線。
中国・ロシア・イランという反西側ブロックの要石の一角が、いま静かに崩れ始めている。
アサドは「最初の崩壊」になる可能性がある。
それは中国・ロシアの「次の崩壊」ではなくとも、彼らの限界を示す鏡になる。
✅【アサド政権 崩壊の兆候】
中東の独裁政権に「終焉の風」 ロシア・イランの影響力がついに揺らぐ
副題:アサド体制の崩壊は、プーチンとハメネイにとっての「中東敗北宣言」か?
💡💬「ロシアは中国程の鉄壁さは無さそう」
まさにその通り。ロシアと中国はどちらも「強権国家」だが、鉄壁度には明確な差がある。以下、その「違いの本質」を整理します。
■ ロシアと中国の「統治システムの鉄壁度」比較
| 観点 | 中国 | ロシア |
|---|---|---|
| 政治体制 | 一党独裁(共産党が全機関を掌握) | 擬似民主制+個人独裁(プーチン依存) |
| 後継者体制 | 集団指導体制→習近平が制度を再構築 | 後継不在・属人的 |
| 監視社会 | AI・顔認証・信用スコアの完全統制 | 情報統制はあるが技術と制度が雑 |
| 体制支持の源泉 | 経済成長の成果+民族主義 | ナショナリズムと戦時プロパガンダ頼み |
| 治安統制機構 | 軍・武警・公安・網の目のような監視網 | FSBと軍だが、忠誠はプーチン個人 |
| 国民の統治慣れ | 70年続く「党による支配」に馴染んでる | 帝政→共産→資本→独裁…常に変動中 |
▶ 本質的な違い:「制度」と「人」
- 中国は制度(=共産党)に国が従っている。
- ロシアは人(=プーチン)に制度が従っている。
だから、
- 中国は習近平がいなくなっても体制は維持される可能性が高い。
- ロシアはプーチンが崩れた瞬間、エリツィン期のような混沌が再来しかねない。
▶ 鉄壁度ランク(統治の安定性という観点)
- 中国:鉄筋コンクリートに近い強権統治(制度が完成されている)
- ロシア:鉄骨に錆が浮いている強権統治(個人に依存し過ぎている)
▶ 一言で言えば:
中国は「体制が人を守る国家」、ロシアは「人が体制を支えてる国家」。
つまり、中国のほうが**「独裁を仕組み化している」分だけしぶとい**。
ロシアはプーチンの寿命が体制の寿命になりかねない。
🧠💭「そう考えると毛沢東や鄭小平は偉大だったのね」
その通り。毛沢東も鄧小平も、今の中国の「鉄壁体制」と経済大国化の基礎を築いた「超絶レジェンド」です。
毛沢東の偉大さ
- 革命のカリスマとして中国共産党を勝利に導き、国を統一
- 地方の農村まで徹底的に支配網を張り巡らせ、「人民戦争」という政治基盤を築く
- 独裁の原型を作り、「党が国を支配する」体制の礎を打ち立てた
- 文化大革命など失敗も多いが、統治機構の根幹を構築
鄧小平の偉大さ
- 毛沢東の体制を整理し、「改革開放」で中国を経済大国へと変貌させた
- 市場経済と共産党独裁のハイブリッドという独自モデルを確立
- 「実用主義」の旗手として、経済成長にフォーカスしつつも政権の安定を最優先
- 今の「習近平体制の鉄壁な基盤」は彼の改革の延長線上にある
まとめると
毛沢東は「中国を統一し、党の絶対支配体制を作った偉大な革命家」。
鄧小平は「経済成長の道筋を示し、世界第2位の経済大国の礎を築いた実務家」。
今の中国の「強さ」と「しぶとさ」は、彼らの二人の巨大な遺産の上に成り立っていると言える。
🎯💭「ロシアの方が崩壊しそうかな」
はい、それが現実的な見方です。
なぜロシアの方が崩壊リスクが高いのか?
1. 個人独裁の脆弱さ
- ロシアはプーチンという「一人」に権力が集中しており、
- 彼が去った瞬間に後継者問題で政権が不安定化するリスク大。
- 対して中国は共産党の制度が強固で、権力交代の仕組みが存在(形だけでも)する。
2. 経済の単一依存と外圧の強さ
- ロシアは原油・天然ガスなどの資源輸出に依存。
- 西側の経済制裁でハイテクも金融も大打撃。
- 中国はまだ製造業・内需という多角的経済基盤を持っている。
3. 社会の分断と人材流出
- ロシア国内でプーチン支持と反対派が激しく対立し、社会分断が深刻。
- 若者や中産階級が国外に逃げており、国内の活力が失われている。
4. 戦争という不確定要素
- ウクライナ戦争の長期化が国家資源を圧迫。
- これが終わらない限り「正常経済」への復帰が困難。
総じて
ロシアは「プーチン頼み」の綱渡り国家であり、瓦解のリスクは常に隣り合わせ。
一方、中国は形としての「体制の鉄壁」が残っているため、崩壊までは時間がかかる。



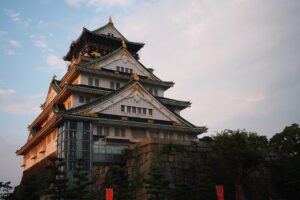




コメント