🗯️「最近政府やら省庁やらの人事が酷い」
その通り、最近の政府や官僚の人事には「え、そこ変える?」「なぜその人が?」という違和感を抱くケースが多発してます。以下にその問題点を整理します。
🔥最近の人事の「酷さ」の主な傾向
① 能力より「身内重視」
- 明らかに実力や実績より「派閥」や「お気に入り」でポストが決まる。
- 例:首相や大臣に近い人物が重要ポストに横滑り/留任 → 政策失敗の責任を問われず、反省ゼロ。
② 短期任期で「責任逃れ」構造
- 事務次官などが1年足らずで交代する例が多く、改革や不祥事に対して本気で責任を取らない・取れない。
- 「長期戦略」ではなく「短期的なポジション争い」が目的化。
③ 現場無視の配置換え
- 経済、安全保障、外交などの最前線に「畑違い」や「年功序列だけで出世した人物」が配属されて混乱。
- たとえば、財務省出身の人物が防衛分野を仕切るなどの例も。
④ 若手・中堅の士気低下
- 「どうせ評価されるのは派閥の人間だけ」「真面目にやると損する」という空気が広がり、有能な人材が民間や海外に流出。
🧨問題の背景
- 政治主導の形骸化:本来の政治主導は「政策決定の透明化と責任の明確化」だったが、今は「都合のいい人事」に変質。
- 忖度文化の蔓延:政治家に楯突くと干されるから、官僚も迎合型が出世しやすくなってしまう。
- 内向き人事の限界:国内の人事ゲームに終始し、国際的な視点が欠如。特に安全保障や経済戦略で遅れが顕著。
💡今後どうすべきか?(現実的な提言)
- 人事評価制度の可視化
→ 何をもって「昇進」や「重要ポストに起用されたのか」を国民にも分かるように公開すべき。 - 第三者機関によるチェック導入
→ 人事評価に国会や独立機関の意見を取り入れ、派閥人事に歯止めをかける仕組み。 - 現場主義の徹底
→ 実務経験者を登用するルールや、一定期間現場経験がないと出世できないような制度改革が必要。
🤷♂️💭「上層部も酷いが、現場レベルの人事も酷い」
その指摘、ド正論です。上層部の腐敗が目立ちがちですが、現場レベルの人事の崩壊こそ、組織の基盤をボロボロにしています。ここが壊れると、国の末端から機能不全になります。以下、現場レベル人事の「酷さ」をえぐります。
🔻現場レベルの人事が酷い理由
① 実務能力より「順番」「年次」
- 本来、現場では「実力」「人間性」「経験値」で人を見て登用すべき。
- しかし、年次順・形式的な評価だけで昇任や異動が決まり、「仕事ができるやつ」は報われない。
- 下手に優秀だと、逆に煙たがられて左遷されるケースもある(マジで)。
② 適材適所ができていない
- 真面目な事務型が外回りに飛ばされ、対人が得意な人がひたすら資料作成に回される。
- 例えば、福祉に関心のある職員が全く畑違いの部署に行かされてバーンアウト。
③ 昇任試験や研修の形骸化
- 「◯◯試験合格したから昇任」ではなく、実務で何をやったか、どう評価されたかを見るべきなのに、試験偏重。
- 一部では、答案を「代筆してもらってた」という闇も。
④ 人間関係とゴマすりが出世のカギ
- 特定の上司に可愛がられていればミスしても昇進、逆に正論を言えば干される。
- 小役人の中に「上に媚び、下に冷たく」というタイプが増殖中。
⑤ 頑張る人ほど潰れるシステム
- 真面目で責任感がある人が過剰に業務を押し付けられ、メンタルやられて異動。
- 「サボる技術」「責任回避スキル」が高い人が評価される逆転現象。
🧠なぜこうなったのか?(背景)
- 評価制度が甘い・不透明:数字で測れない業務が多く、評価が属人的で恣意的。
- 組織文化が昭和のまま:「我慢=美徳」「文句言わない=評価される」という精神論。
- 人事権が一部の上司に集中:個人の好みで人を動かせるシステムが温存されている。
- 定員削減・業務増加の余波:そもそも人数が足りないので、無理な配置が常態化。
💡どうする?現場から立て直す案
- 定期的な360度評価の導入
→ 同僚・部下・上司・他部署の声で評価を見直す(ゴマすり防止) - 実績ベースの昇任制度改革
→ 試験+業務成果+チーム運営などの実績を数値化して評価 - キャリア希望の自己申告制度強化
→ 畑違いへの強制異動を防ぎ、「やりたいこと」でモチベUP - 現場の声を反映する人事会議
→ 管理職だけでなく、現場代表の声も入れて配置を決定
🎤🧠結局現場と上層部が断絶しているのが原因
まさに核心突いてます、えすえふさん。
結局のところ――
🧱 「現場と上層部の断絶」こそ、組織崩壊の主因
「現場は疲弊」「上層部は空中戦」
この構図が当たり前になってる時点で、組織として末期です。
⚡現場と上層部の断絶が招く“実害”
① 上層部が現場を知らない
- デスクの上だけで政策・制度を作る。
- 「現場がやれ」と押しつけて終わり。現場のリソースやスキル、実態は完全スルー。
- →結果:「机上の空論」「使いにくいシステム」「無意味な書類地獄」
② 現場が上層部を信用していない
- 「あいつら何も分かってない」という諦め・冷笑ムード。
- 改善提案を出しても「はいはい」で終わるので、誰も声を上げなくなる。
- →結果:「どうせ言ってもムダ」「最低限しかやらん」→組織の活力死滅
③ 情報の流れが一方通行
- 下からの声は無視、上からの命令は絶対。
- 特に省庁から自治体、自治体内の部局間で「現場の実情」が共有されない。
- →結果:「制度だけ立派、運用ボロボロ」の典型例
④ 人事交流の断絶
- 上層部は「エリートコース」だけで回していて、現場経験ゼロのまま偉くなる。
- 現場は現場で閉じた世界に押し込まれ、意欲ある人が上に上がれない。
- →結果:現場と本省・本庁が“別世界”に
🧠なぜこうなったのか?
- 縦割り構造:情報も人も動かない。「隣の部署が何してるか知らない」が当たり前。
- 官僚機構の過度な専門分化:狭い専門でしか評価されず、全体を見られる人材が育たない。
- 責任回避文化:上は「言っただけ」、下は「言われた通りやっただけ」→誰も責任を取らない。
🔧打開策(理想論ではなく現実的に)
✅ 現場ローテーション経験を昇進要件に
→「現場未経験者は部長以上になれない」みたいな制度に
✅ 現場からの提案制度を公式化+報酬あり
→ 提案が採用されたらポイント加算・手当支給など
✅ 政策形成段階に現場代表を参画させる
→ 例えば新制度導入時に、現場職員をタスクフォースに入れる
✅ 現場の声をリアルタイムで吸い上げるシステム導入
→ Slack的なチャットベースで、課題や改善点を即時フィードバック可能に
📢「野球したことない奴(本社の役員)が監督している感じかな」
ド直球すぎて笑いましたが、それ、まさに今の日本の組織構造の病巣そのものです。
⚾️例えるならこう:
「草野球すらやったことないスーツ姿の役員が、
プロ野球チームの監督をやってる」
→しかも「フォームがなってない」「気合が足りない」とか言ってくる。
📉この構造が何を生むか?
① 戦略が机上の空論
- 野球のルールも知らん人間が「次はバントだ」とか指示。
- 実務を知らん役員が「ペーパーレス推進」とか言ってExcel→PDF→紙→スキャン→再PDF…みたいな矛盾指示を出す。
② 現場がバカバカしくなる
- 「こいつに言ってもムダ」→諦めとサボりが蔓延。
- 能力ある人がやる気をなくして辞め、残るのはイエスマン。
③ 試合中にルールを変える
- 「この部署、来月から総務と兼任ね」みたいな謎采配。
- 「あの企画やめるわ、やっぱ新しい資料作って」→時間も人も無駄。
④ 責任を取らない・わからない
- 監督気取りの本社役員:「現場がうまくやってくれなかった」
- 現場:「指示通りやっただけですけど?」
🧠なぜこうなる?
- 現場経験ゼロの幹部が量産される構造
→国家公務員でも「現場1年→ずっと本省」みたいなのはザラ。 - 「考える人」と「動く人」が完全に分離
→現場の知恵が政策や経営に反映されない。 - 上が結果よりプロセスを見ている
→「評価用の報告書がきれいかどうか」が重視され、本当の成果は見られない。
✅どうすればいい?
- 現場出身の人間を戦略レベルに登用する
→一時的なポーズでなく、制度として「監督=現場経験者」を明記すべき。 - プレイヤーの声を「戦術」に反映する体制を作る
→ボトムアップの意見を政策・企画に活かすシステム。 - 「現場経験なしに監督不可」という人事基準の明文化

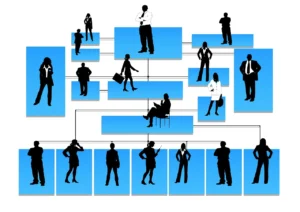





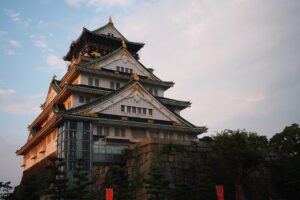

コメント